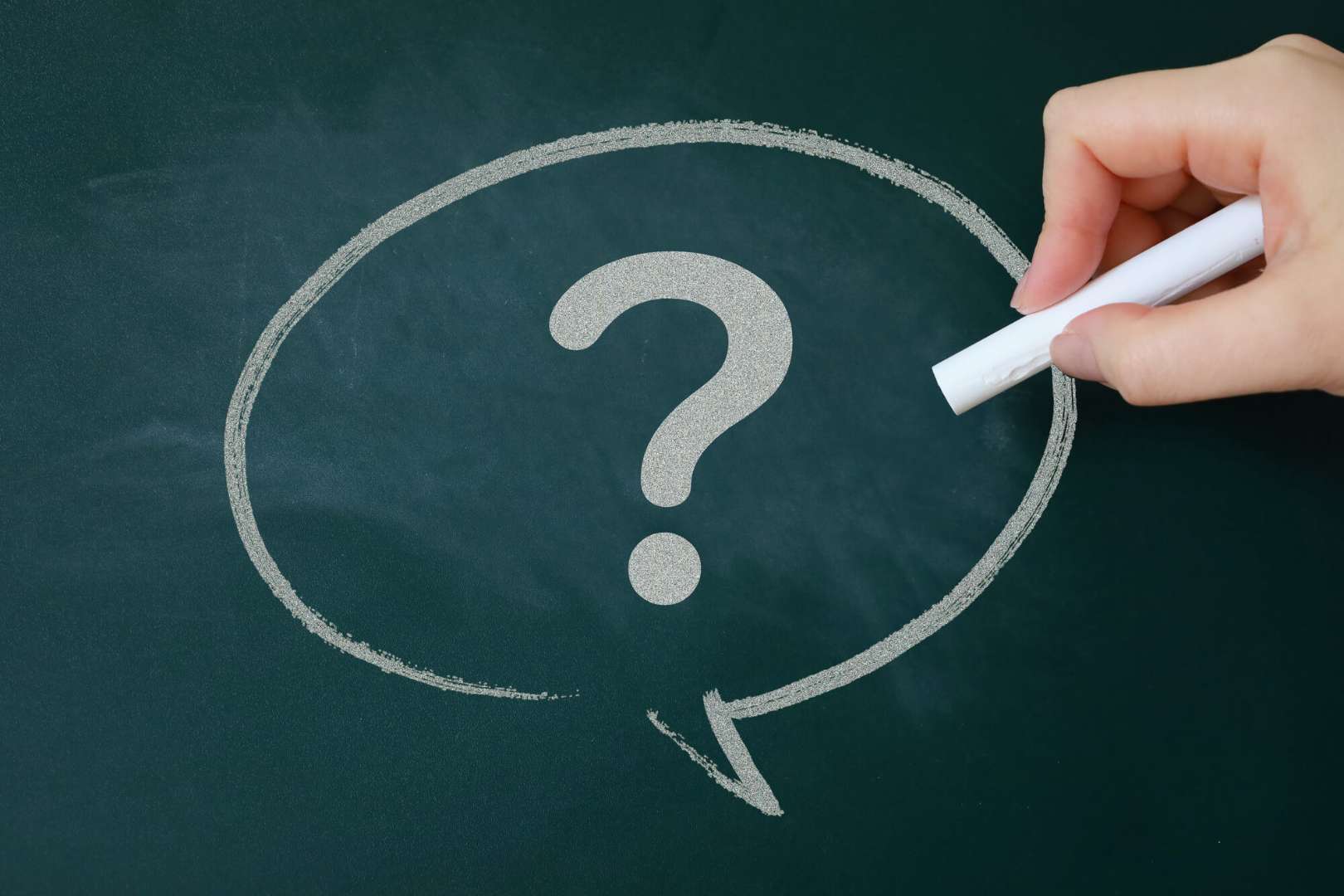「外構屋って、きつい仕事のわりに儲からないんでしょう?」
そんな声を耳にして、この仕事に興味を持ちながらも、一歩を踏み出せずにいる方もいるかもしれません。あるいは、すでに職人として働きながら、将来の収入に漠然とした不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
たしかに、外構業界には昔から根強く残る課題があり、それが「儲からない」というイメージにつながっている面は否定できません。しかし、その言葉だけを鵜呑みにして、ものづくりの喜びや、お客様の暮らしそのものを豊かにできるこの仕事の大きな可能性を諦めてしまうのは、あまりにもったいないことです。
では、なぜこのようなイメージが生まれてしまうのでしょうか。そして、同じ業界で働きながらも、お客様から深く感謝され、高い収入とやりがいを両立させている人たちがいるのはなぜなのでしょうか。
その違いは、業界の構造を正しく理解し、自分自身の働き方や身を置く環境を、確かな視点を持って選んでいるかどうかにあります。この記事では、噂の真相から、未来を切り拓くための具体的な働き方まで、一つひとつ順を追って考えていきたいと思います。
噂の真相:なぜ外構業界は「儲かりにくい」と言われるのか
「外構屋は儲かりにくい」という声には、残念ながらいくつかの構造的な理由が存在します。この問題を避けて通ることはできませんので、まずはその背景を冷静に見ていきましょう。キャリアを考える上で、光だけでなく影の部分も知っておくことは非常に大切です。
ピラミッド型の業界構造
大きな要因の一つに、建設業界全体に見られる重層的な下請け構造が挙げられます。お客様から直接仕事を受ける「元請け」がいて、その下に一次、二次、場合によっては三次と下請け業者が連なるピラミッドのような形です。
この構造では、仕事が下の階層へ流れるたびに中間の手数料が引かれていくため、最終的に現場で汗を流す職人の手元に残る利益は、どうしても少なくなってしまいがちです。とくに、特定の元請け会社からの仕事に依存している場合、立場が弱くなり、厳しい条件で仕事を受けざるを得ないという状況も生まれやすくなります。
価格で選ばれやすい現実
外構工事は、家を建てるときの最終段階で行われることが多く、全体の予算が厳しくなりがちな部分でもあります。そのため、お客様によってはデザインの良さや品質の高さよりも、どうしても価格の安さが業者選びの決め手になってしまうケースが少なくありません。
結果として、業者間での厳しい価格競争が起こり、本来必要な手間や材料費を削らなければならない状況に陥ってしまうことがあります。これでは、良いものを作ろうという職人の意欲も削がれてしまいますし、会社として十分な利益を確保することも難しくなります。
天候と身体に左右される仕事
外での作業が中心となるため、どうしても天候に仕事の進み具合が左右されます。雨の日が続けば工事は進まず、その間の収入が不安定になることもあります。また、夏は暑く冬は寒いという環境で、体力を使う仕事であるため、年齢とともに同じように働き続けることが難しくなる可能性も考えなければなりません。時間をかければかけるほど収入が増えるわけではない、労働集約型のビジネスモデルならではの難しさがここにあります。
しかし、それは業界のすべてではない。高単価・高利益を実現する職人たちの共通点
前章で述べたような厳しい現実は、確かに業界が抱える一側面です。しかし、それだけで「外構屋はやはり儲からない」と結論づけるのは早計です。なぜなら、こうした構造的な課題を乗り越え、お客様から高い評価を受け、しっかりと利益を上げている職人や会社も数多く存在するからです。
彼らは一体、何が違うのでしょうか。それは、単に言われた通りに「作業をする人」で終わるのではなく、お客様に対して独自の「付加価値」を提供している点にあります。
暮らしをデザインする提案力
高い評価を得ている職人たちは、お客様の漠然とした要望をただ形にするだけではありません。「ご家族の構成やライフスタイルを考えると、こちらの方が動線もスムーズで使いやすいですよ」「将来、車が増える可能性も考えて、このような設計はいかがでしょうか」といった、プロならではの視点で積極的に提案を行います。お客様自身が気づいていなかった課題を見つけ、その解決策を示すのです。
このような期待を超える提案は、価格の比較だけで判断されるステージから一線を画し、「ぜひ、あなたにお願いしたい」という強い信頼につながります。これは、もはや単なる作業ではなく、お客様の暮らしそのものを豊かにデザインする、コンサルタントのような役割と言えるでしょう。
専門知識に裏打ちされた技術力
もちろん、素晴らしい提案を形にするための、確かな技術力が不可欠であることは言うまでもありません。例えば、敷地の水はけを緻密に計算した勾配のつけ方、何十年も先を見据えた耐久性の高いブロックの積み方、植える植物の成長後をイメージした配置など、完成直後には目に見えにくい部分にこそ、プロの技と経験が光ります。こうした専門知識に裏打ちされた技術は、一朝一夕で身につくものではなく、誰にも真似できない大きな価値となります。
現場全体を見渡す管理能力
優れた職人は、自分の作業範囲だけでなく、工事全体の流れを深く理解しています。予算の管理からスケジュールの調整、他の職人との円滑な連携まで、現場監督のような役割をこなせる人材は、どの会社でも非常に重宝されます。現場全体をスムーズに進める管理能力があれば、無駄なコストや時間を削減でき、結果として会社の利益に大きく貢献することができるのです。
価格競争から抜け出し、「価値」で選ばれる職人になるためのステップ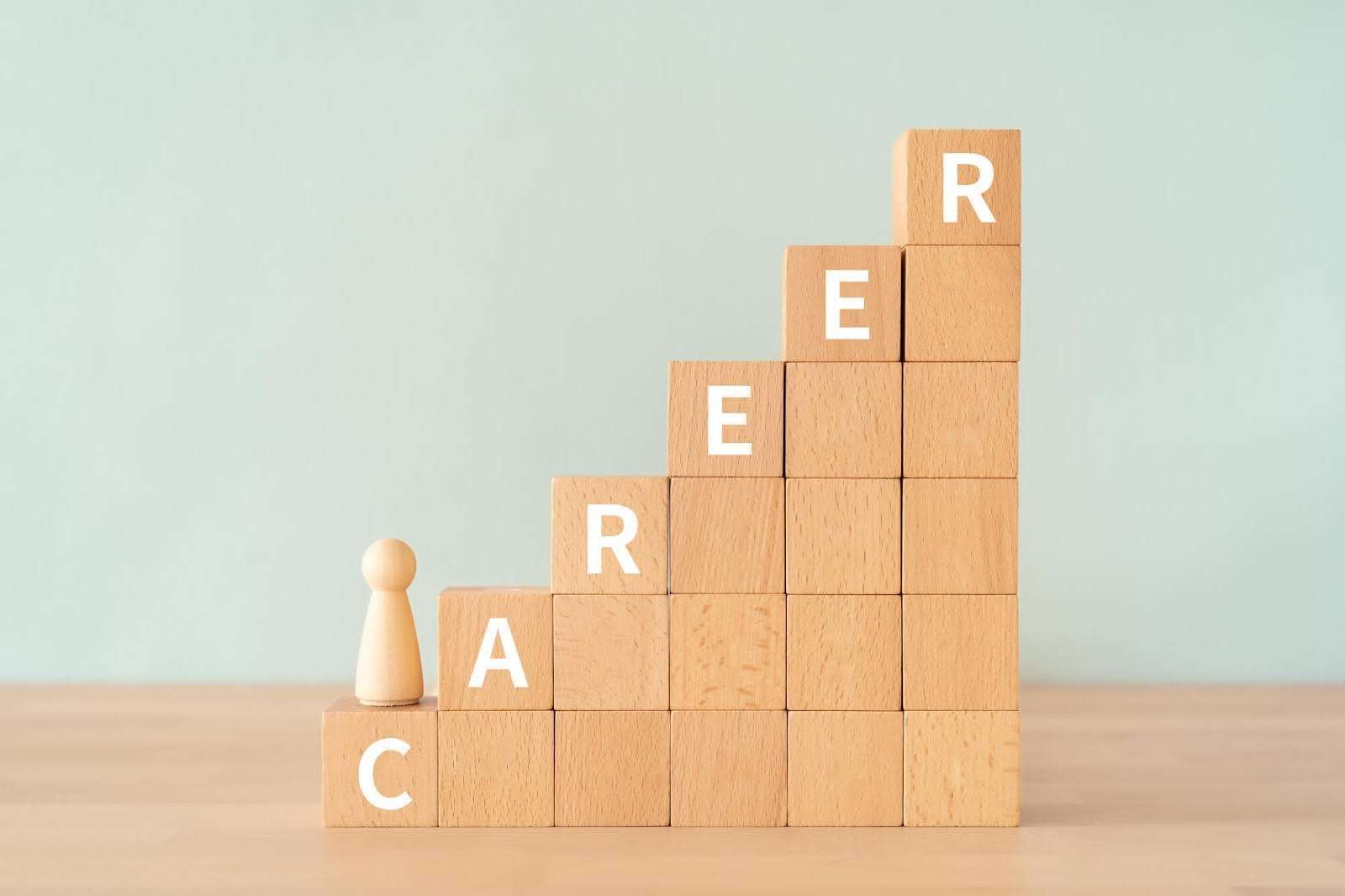
では、どうすれば価格競争の渦から抜け出し、お客様から「価値」で選ばれる職人になれるのでしょうか。それは、受け身で仕事を待つのではなく、自らの市場価値を高めるために、能動的に学び、行動していく姿勢を持つことから始まります。ここでは、そのための具体的なステップを考えてみましょう。
専門性を深める「スキルの掛け合わせ」
一つの技術を極めることはもちろん大切ですが、これからの時代は複数のスキルを掛け合わせることで、あなたの価値は何倍にも高まります。例えば、ブロックを積む技術に加えて、CADソフトを使ってお客様の前で立体的な図面を描きながら説明できれば、イメージの共有が格段にスムーズになり、信頼感が増すでしょう。
また、施工技術だけでなく、植物や照明に関する専門知識があれば、「夜の雰囲気も素敵に見せるライティング」や「四季の移ろいを楽しめる植栽計画」といった、より付加価値の高い提案が可能になります。単なる職人ではなく、空間全体のデザイナーとしての視点を持つことが、他にはない強みとなるのです。
信頼を形にする「資格の取得」
あなたの技術や知識を客観的に証明してくれるのが、資格です。例えば「造園施工管理技士」や「ブロック塀診断士」といった資格があれば、お客様は安心して仕事を任せることができます。資格取得の過程で得られる体系的な知識は、日々の仕事の質を向上させる上でも大いに役立つはずです。
会社によっては資格取得を支援してくれる制度を設けているところもありますので、そうした環境を積極的に活用することも、キャリアを築く上で賢い選択と言えるでしょう。
働き方を主体的に「選択する」
将来のキャリアを考えたとき、選択肢は一つではありません。経験を積んで、いずれは独立し、自分の理想とする外構を手がけるという道もあります。自分の裁量で仕事を進め、利益を直接得られるのは大きな魅力です。
一方で、元請けとしてお客様と直接向き合い、デザインから施工までを一貫して手がける会社に所属するという選択も非常に有効です。良い会社であれば、個人の力だけでは難しい大規模な案件に携われたり、チームで知識や技術を共有しながら成長できたりと、多くのメリットがあります。大切なのは、自分がどちらの道に進みたいのかを考え、そのために今何をすべきかを見据えることです。
【企業の選び方】職人の成長を支援し、価値を正当に評価する会社とは
個人の努力やスキルアップはもちろん重要ですが、どの会社で働くかという「環境選び」が、あなたの収入や成長のスピードを大きく左右することも忘れてはなりません。価値を正当に評価し、職人一人ひとりの成長を本気で考えてくれる会社には、いくつかの共通する特徴があります。
お客様と直接向き合えるか
まず確認したいのは、その会社が手がける仕事のうち、元請け、つまりお客様から直接依頼される案件がどれくらいの割合を占めているかです。元請けの仕事が多ければ多いほど、職人がお客様の声を直接聞き、提案する機会に恵まれます。お客様の喜びをダイレクトに感じられることは、仕事のやりがいにつながりますし、中間マージンが発生しないため、利益を社員に適正に還元しやすいという側面もあります。
どんな「ものづくり」をしているか
その会社のウェブサイトにある「施工事例」は、企業選びにおける宝の山です。そこに掲載されている写真からは、単に工事の規模や数だけでなく、その会社がどのようなデザインを得意とし、どんな「ものづくり」を大切にしているかという哲学まで読み取ることができます。一つひとつの仕事にこだわりが感じられ、あなたの感性に響くような事例が多ければ、そこはきっとあなたにとって良い環境である可能性が高いでしょう。
人を育てる文化があるか
未経験者であれ経験者であれ、人を大切にし、長期的な視点で育てようという文化があるかどうかも極めて重要です。例えば、社内での勉強会が定期的に開かれていたり、資格取得のための費用を会社が負担してくれたりといった制度が整っているかは、その会社の姿勢を測る一つの指標になります。面接などの機会には、どのような研修制度があるのか、先輩たちはどのようにスキルアップしていったのかを具体的に質問してみると良いでしょう。
どんな想いで、どのような外構を手がけている会社があるのか、一度じっくりと見てみるのも良いかもしれません。
https://www.nagisagikenn.jp/works
まとめ:「儲からない」を嘆くのではなく、自ら「儲かる」キャリアを設計しよう
「外構屋は儲からない」という言葉は、あくまで業界の一側面を切り取ったものに過ぎません。その言葉をただ受け入れてしまうのか、それともその構造を理解した上で、自らの力で乗り越えていくのか。どちらの道を選ぶかで、外構職人としての未来は大きく変わってきます。
この記事でお伝えしてきたように、これからの時代に求められるのは、言われたことをこなすだけの「作業者」ではありません。お客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、プロならではの知識と技術で期待を超える価値を提供する「パートナー」です。
そのためには、常に学び続ける意欲を持ち、スキルを掛け合わせ、自分自身の市場価値を高めていく努力が不可欠です。そして同時に、あなたの成長を後押しし、その価値を正当に評価してくれる会社を、あなた自身の目でしっかりと見極める必要があります。
変化の時代は、常に新しいチャンスが生まれる時代でもあります。どうか、根拠のないイメージに惑わされることなく、あなた自身の力で、やりがいに満ちた豊かなキャリアを築いていってください。
もし、この記事を読んで、外構の仕事についてさらに深く知りたくなったり、具体的な相談をしてみたくなったりしたなら、気軽に声をかけてみてください。